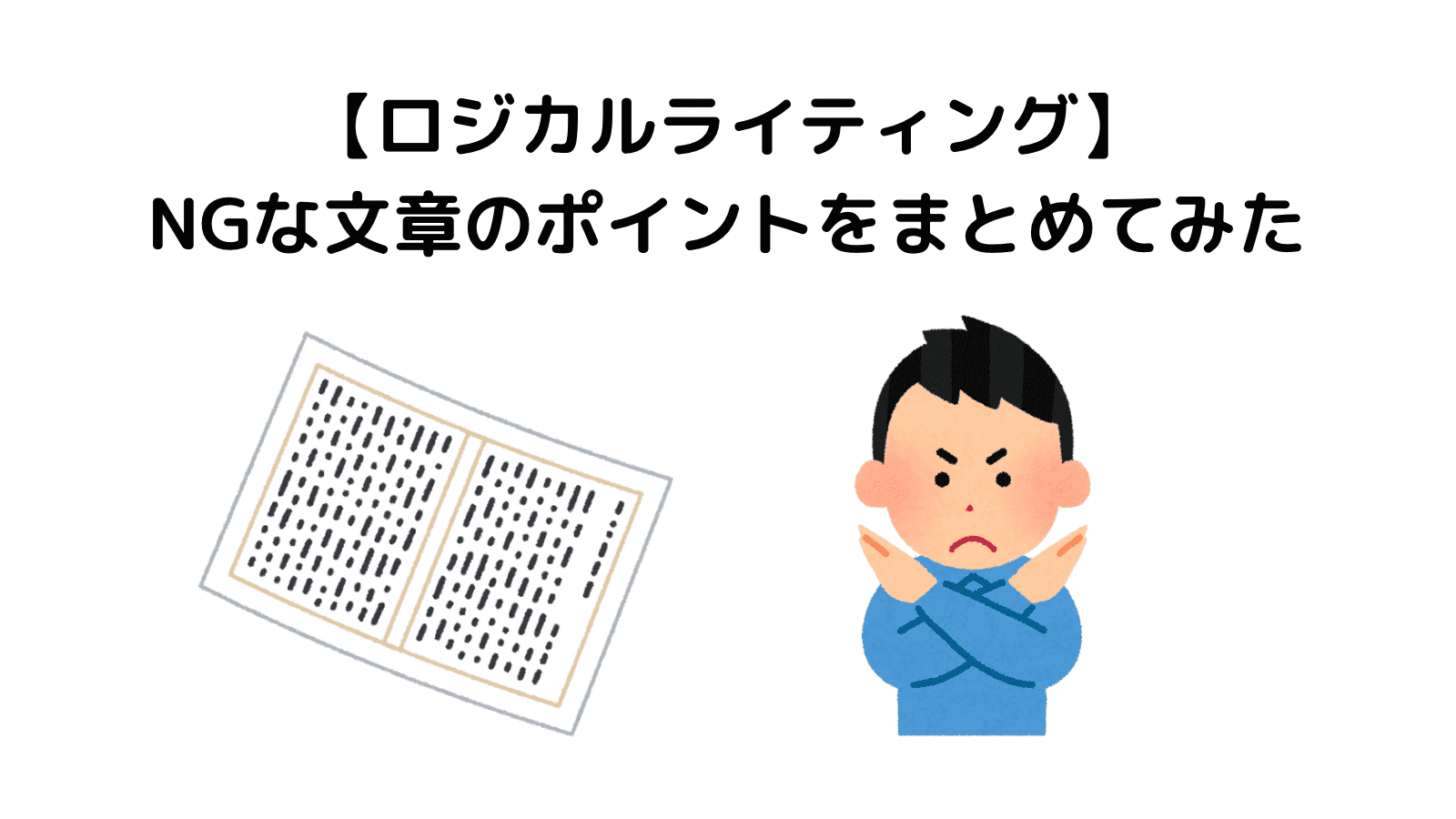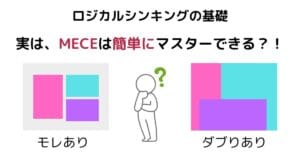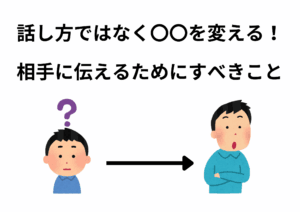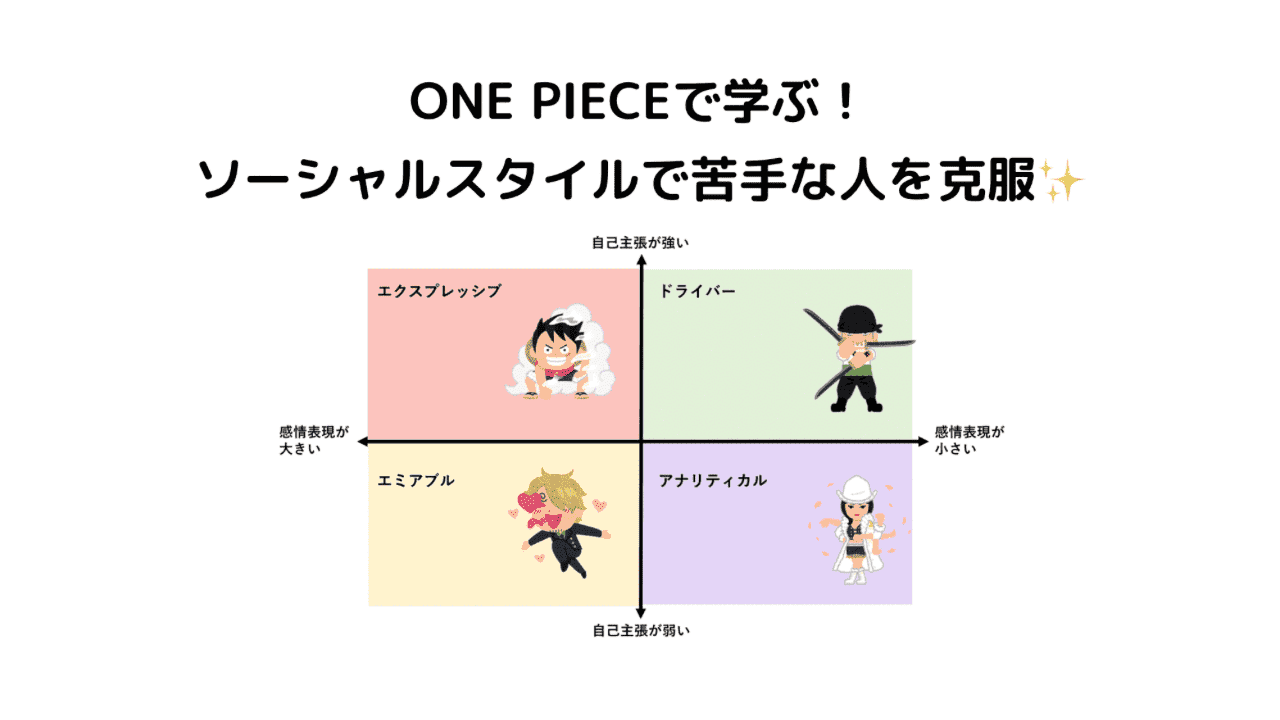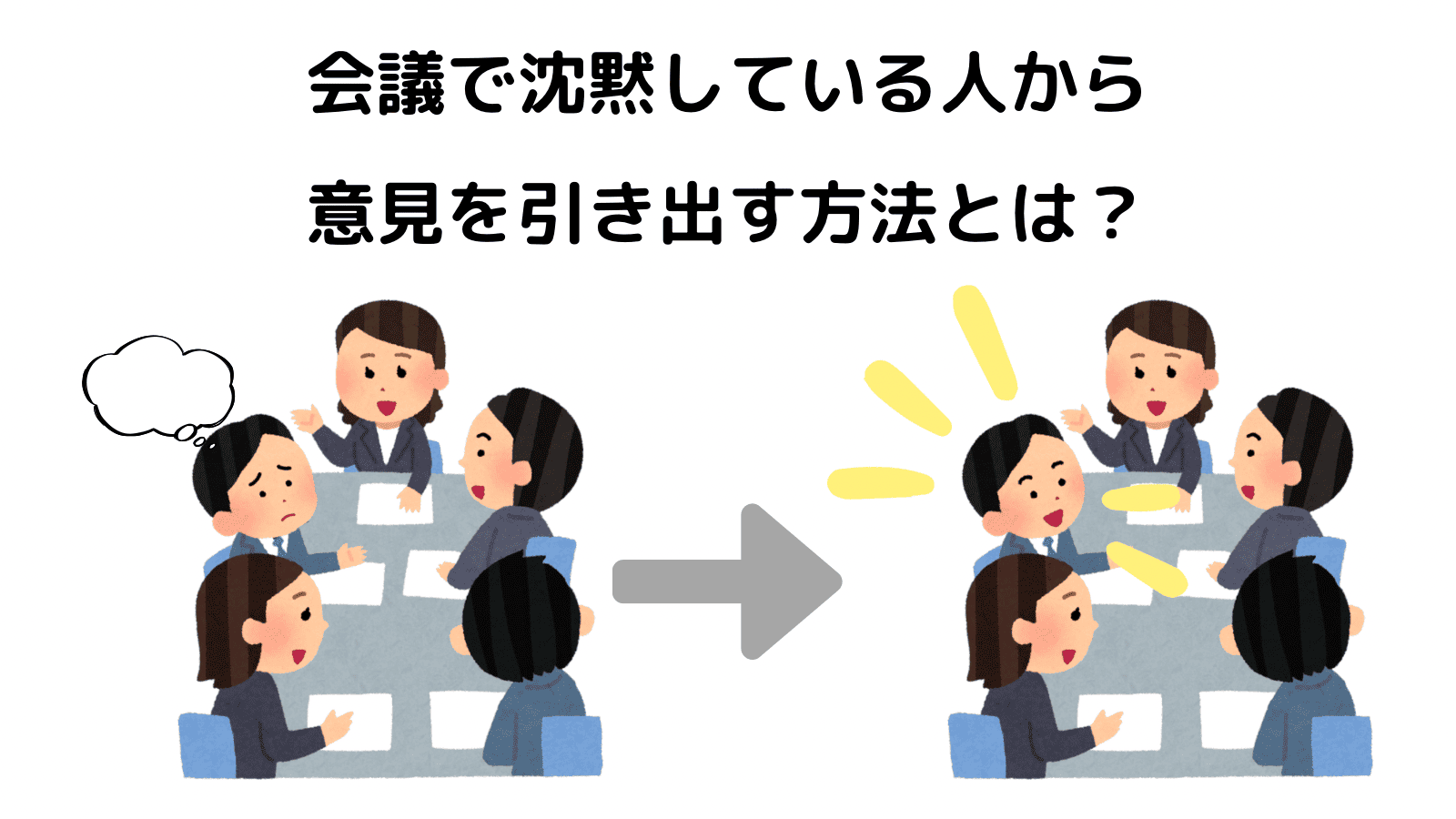- 文章を書いても「なかなか伝わらない」と悩んでいる
- ビジネスメールや報告書、企画書などで誤解が生じやすい
- 自分の書いた文章がなぜ伝わらないのか、その原因が分からない
- より論理的で分かりやすい文章を書くための具体的な方法を知りたい

しろろ
こんにちは! しろろです。
文章作成で相手に正確な意図が伝わらなくて、悩んだ経験はありますか?
「ビジネスメールで意図が伝わらない」「報告書が差し戻される」「SNSで誤解が生じる」など、文章で困った経験があるのではないでしょうか。
ビジネスメールや企画書、SNSでの発信など、文章を書く機会はたくさんありますよね。
頑張って書いたのに、読み手にきちんと伝わらないと、時間も労力もムダになってしまいます。
文章を「わかりやすい」と感じるかどうかは、実は読み手のストレスに直結しており、読みにくい文章は途中で読むのをやめてしまいがち。
だからこそ、相手に「伝わる」文章を書くスキルは、円滑な人間関係や仕事の成果に直結すると言えるでしょう。
この記事では、読み手が「あれ?」と感じてしまうロジカルライティングのNG例と、その具体的な回避術を5つのポイントに絞ってご紹介します。
この記事を読めば、あなたの文章は劇的に改善され、スムーズなコミュニケーションが実現するはずです。
ロジカルライティングによる文章作成でのNG集
文章でよくある「伝わらない」原因は、以下の4つのポイントに集約されます。それぞれなぜNGなのか、そしてどう改善すればいいのかを具体的に見ていきましょう。
限定表現を使う
下記のような言葉を使うときは、文章のロジックが崩れている可能性があります。
- できる
- 全て
- 全く~ない
- ~である
なぜNG?
これらの断定的な言葉は、一見すると説得力があるように見えます。
しかし、現実世界は不確実性に満ちており、常に例外や条件が存在するため、これらの表現を多用すると、かえって情報の正確性を損ない、読み手に誤解や不信感を与える可能性があります。
たとえば、どこから見ても同じ状態を表す球体のようなものは、現実にはごく稀です。
ある視点から見れば球体に見えても、別の視点からは円錐や円柱である可能性もあります。

いろいろな立体のイラスト/引用元:いらすとや
回避術
「~の可能性がある」「~の傾向がある」「多くの場合」「~と推測される」「~と考える」など、状況に応じて柔軟性を持たせた表現に置き換えましょう。
これにより、情報の正確性を保ちつつ、読み手との認識のズレを防ぐことができます。
悪い例:新しい技術を業務で応用することで、業績に貢献できる。
良い例:新しい技術を業務で応用することで、業績に貢献する可能性がある。
しろろの実体験
以前、研究技術の報告書で「新しい技術を業務で応用することで、業績に貢献できる」と表現したら、上司に修正されました。
最新技術を業務に使うことはできても、それが直接業績に結びつくとは限らないため、不適当だと指摘されたんです。
市場状況や競合他社の動向など、様々な要因が絡むため、安易な断定は避けるべきだと学びました。
ムダな言い直し・接続詞がある
なぜNG?
同じ言葉の繰り返しや、不要な接続詞が多い文章は、冗長に感じられ、読者の集中力を削いでしまいます。
伝えたいメッセージの核心がぼやけてしまい、理解までに時間がかかるため、結果的に「わかりにくい」文章になってしまうのです。
簡潔な文章は、読者の負担を減らし、理解度を高めます。
回避術
「一文一義」を意識し、修飾語を減らす、重複表現を避けるといった工夫が有効です。
また、論理的な構成になっていれば、接続詞がなくてもスムーズに読める文章になります。
悪い例:私の趣味はランニングです。なぜなら、ランニングをすると気分がスッキリするからです。
良い例:私の趣味はランニングです。(走ると)気分がスッキリするからです。
「なぜなら」のような接続詞は、前後の文脈が論理的に繋がっていれば、必ずしも必要ではありません。
また、重複する言葉は代名詞に置き換えたり、別の表現を使ったりすることで、文章がすっきりします。
否定文を使う
なぜNG?
否定文は遠回しな表現になりがちで、読者が内容を理解するまでにワンクッション必要となります。
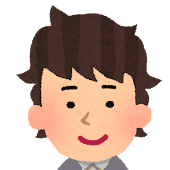
男性A
「私はオクラが嫌いだ」
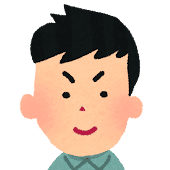
男性B
「私はオクラが好きではない」
前者の方が理解しやすいと感じた方が多いのではないでしょうか。
特に二重否定などは読者の混乱を招きやすく、「結局何が言いたいんだろう?」と思わせてしまいます。
肯定文はストレートに意味を伝えるため、読者はよりダイレクトに内容を理解できます。
回避術
伝えたい内容を、常にポジティブな言葉で表現できないかを考えましょう。
悪い例:〇〇の測定ができないと、▽▽の有効性が分からない。
良い例:〇〇の測定ができると、▽▽の有効性が分かる。
「~できない」は「~が難しい」、「~しない」は「~を控える」「~を中止する」など、状況に応じて肯定的な言葉に言い換えることを意識してみてください。
ゆらぎ表現がある(人によって文章の意味が変わる)
なぜNG?
「検討します」「善処します」「~と捉えています」「~と思われます」など、人によって解釈が変わる「ゆらぎ表現」は、コミュニケーションの齟齬を生み、誤解や手戻りの原因となります。
特にビジネスシーンにおいては、信頼性の低下や業務の遅延につながるため、極力避けるべきです。
回避術
「誰が読んでも同じ意味に受け取れる」ように、固有名詞、日時、数値、具体的な行動などを明確に示しましょう。
これにより、意図が正しく伝わり、スムーズな意思疎通が可能になります。
悪い例:検討します(何をやるのか不明確である)。
良い例:M月D日に〇〇の実験を行います(誰が聞いても一義に決まる)。
しろろの体験談
上司に一番最初に教えてもらったのが「ゆらぎ表現NG」でした。
多様な考え方を持つ人々と働くからこそ、誰にでも同じ意味で伝わる文章が必要だと痛感しましたね。
あいまいな言葉ではなく、具体的な行動や期日を明示することで、お互いの認識のズレを防げるようになります。
情報の過不足がある
なぜNG?
情報が多すぎると、読者は何が重要なのかを見失い、疲れてしまいます。
逆に情報が少なすぎると、読者は理解できず、質問や確認の手間が増えます。
どちらの場合も、読者の負担となり、伝えたいことが伝わりにくくなります。
回避術
読者が必要としている情報は何かを常に意識し、「過不足のない情報量」を心がけましょう。
具体的には、結論から述べ、その理由や根拠を簡潔に示し、必要に応じて具体例を挙げる「PREP法(Point, Reason, Example, Point)」などを活用すると効果的です。
悪い例(情報過多):
今回のプロジェクトでは、A、B、C、D、E、Fの6つの課題があり、それぞれについて詳細な分析を行いました。
Aについては市場調査の結果、〇〇が判明し、Bについては競合他社の動向から△△が明らかになりました。
Cについては、顧客アンケートにより□□という意見が多く…
良い例(整理された情報):
今回のプロジェクトにおける主要課題は3点です。
第一に、市場のニーズと製品との間にギャップがあることが判明しました。
次に、競合他社の新製品投入により、既存製品の競争力が低下している現状があります。
最後に、顧客満足度調査の結果、アフターサービスの改善が急務であると判明しました。
まとめ
今回ご紹介した5つのポイントを意識するだけで、あなたの文章は劇的に変化します。
ぜひ、次回の文章作成から以下のチェックリストを活用してみてください。
- 限定表現を使っていないか?(「できる」「全て」などを疑う)
- ムダな言い回しや接続詞はないか?(一文一義を意識する)
- 否定文ではなく肯定文で表現できているか?
- 誰が読んでも同じ意味に受け取れるか?(日時・数値・具体的な行動を明記)
- 情報に過不足はないか?(結論から伝え、具体例で補足する)
文章を書き終えた時点で読み直し、もし「伝わりにくいかも?」と感じる表現があれば、このチェックリストを使って修正していくとよいでしょう。
最後に
同じ内容を文章で表すとしても、使用する言葉によって読み手の受ける印象が大きく変わります。
文章を書き終わった時点で読み直し、引っかかる表現があれば修正していくとよいでしょう。
ロジカルに考える方法を学びたい方は以下の記事もおすすめです。
私自身、まだまだ文章作成が下手ですが、あなたに有益な情報を届けられるよう日々精進してまいります。
この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!
X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
引き続きよろしくお願いいたします!