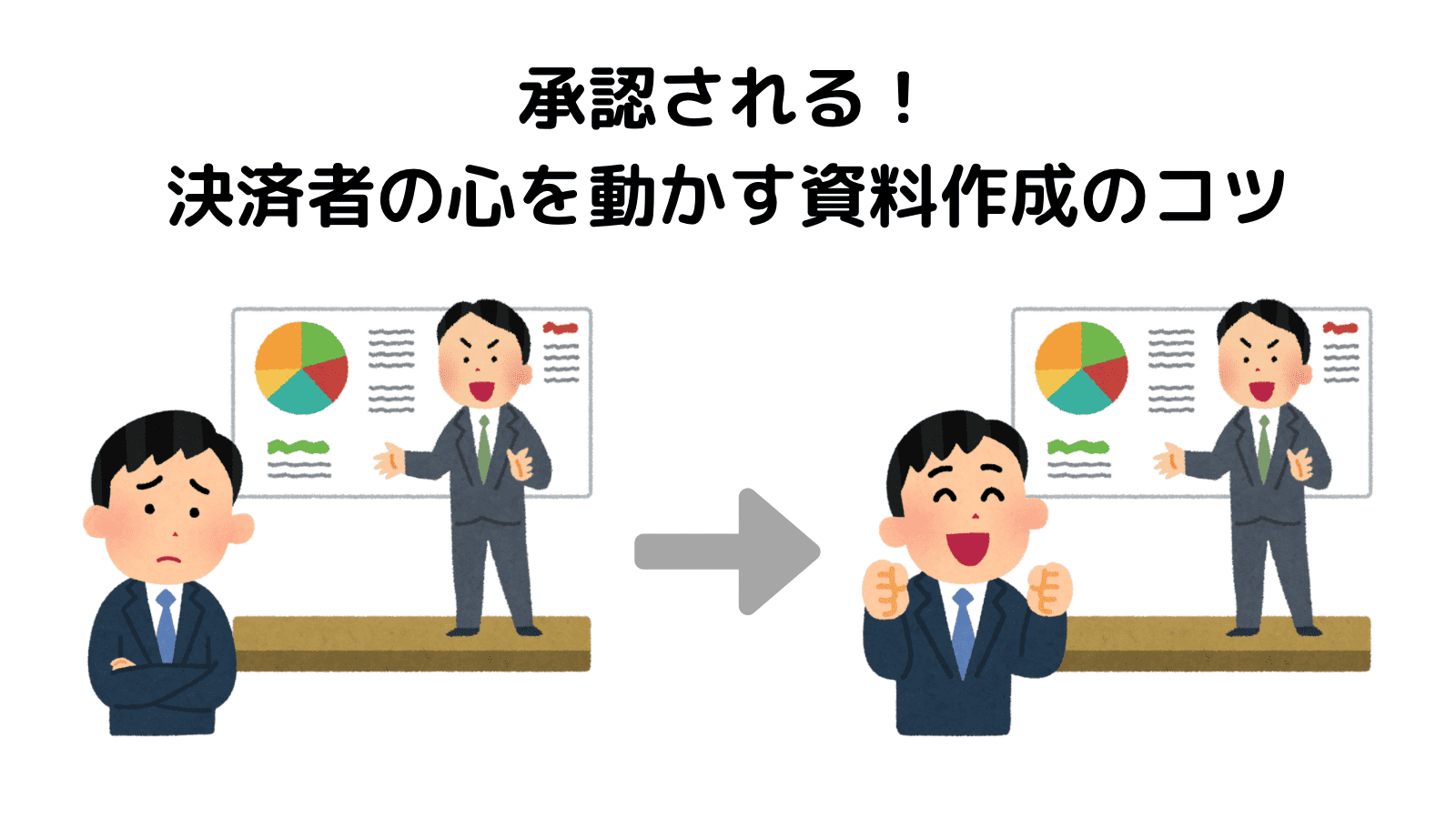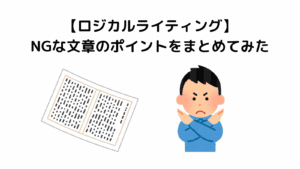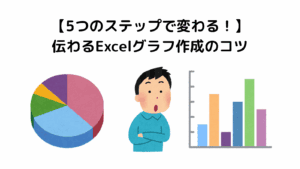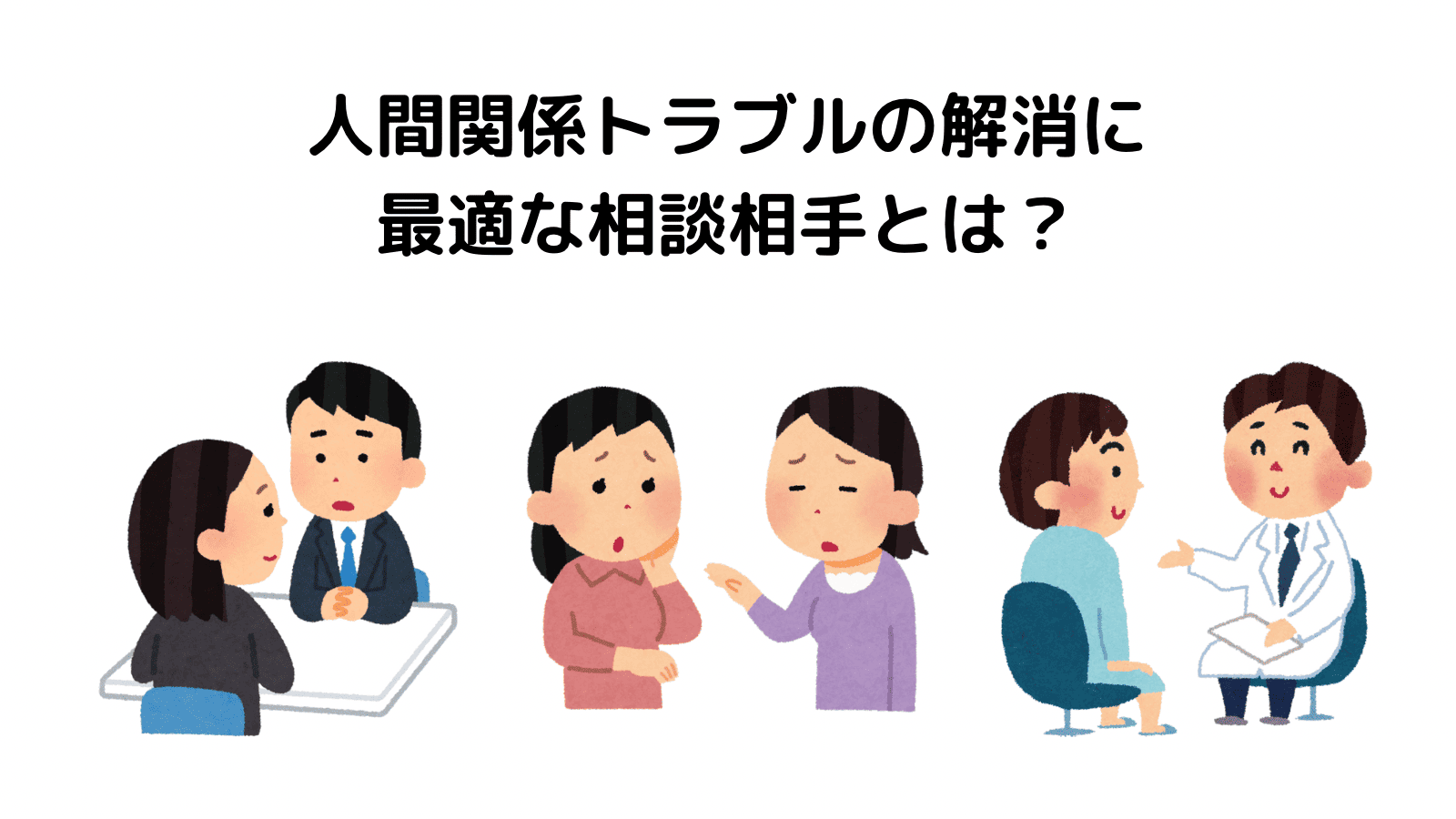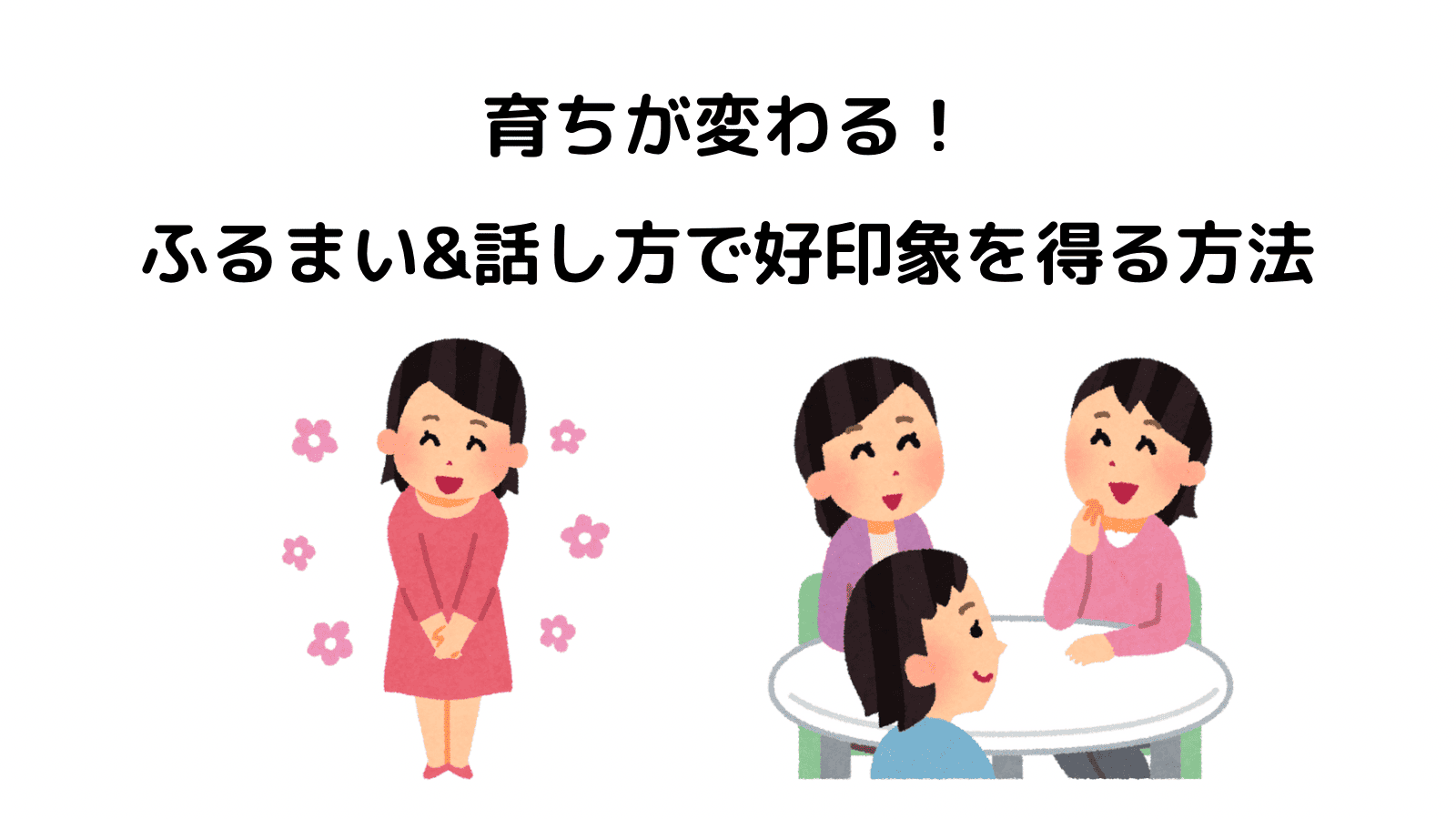- なぜ資料が通らないのか?
- 上司の感情に届く工夫とは?

しろろ
こんにちは、しろろです。
「また却下された…」
何度も上司に企画書を提出しているのに、なかなか承認が下りない。
そんな状況に悩んでいませんか?
実は、プレゼン構成を少し変えるだけで、あなたの企画は劇的に通りやすくなるかもしれません!
私もかつて、上司から「目的がわからない」「結局何がしたいの?」と何度も却下されてきました。
でもある時、「伝え方の構成」を変えるだけで企画が即日承認されたばかりか、なんと他部署から『資料作成のお手本』として紹介されるようになりました。
この記事では、上司がYESと言いたくなるプレゼン資料の作り方をテンプレ付きでわかりやすく紹介します。
ぜひ、皆さんのスライド作りに役立てて、職場での評価と成果を向上させてください。
上司に却下される資料の3つの共通点
提案内容は適切なのに承認されない原因は、以下の3つが考えられます。
何を伝えたいか分からない
タイトルは立派なのに、中身を読んでも「結局何をしたいのか」が伝わらない資料になっていませんか?
たとえば、『今期の営業戦略について』というタイトルだけで、中身は施策が並ぶだけの場合、この発表の目的が受け手には理解しにくいです。
感情に訴えていない
論理は通っていても、「上司の不安」や「組織のメリット」に触れていないと心は動きません。
たとえば、『コスト削減案』を提案する際、単に削減額を並べるだけでなく、『削減できた費用で、社員の働きがい向上施策を実施できます』といった上司や組織のメリット(感情に訴えかける点)を強調します。
このような発表方法を「ロジカルプレゼンテーション」と呼び、提案を角度高く通すために有効です。
正論をぶつけず、相手の感情を意識した発表をすることで、自分の意見を受け入れてもらいやすくなります。
「断る理由」を与えてしまっている
承認したくない人は、わずかなミスでも理由にして断ってきます。
構成のズレ、表現の曖昧さ、誤字といった細部の粗は「減点材料」として見られるのです。
減点されない資料で発表することで、相手に否定される隙を作らなければ、その提案は承認されるはずです。
通る資料はこう作る!上司に刺さる構成4ステップ
資料作成のコツを4つご紹介します。
1. 最初と最後に、発表内容の概要を伝える
表紙スライドの次に、発表概要のスライドを用意する
最初に結論を出すことで、聞き手は「何を聞くのか」が明確になります。
15分以上の発表だと、結論が出るまでに時間がかかるので、話し手が伝えたい事がすぐに分からず、聞き手は疲れてしまうからです。
「結論」を先に知れると、安心して話者の発表を聞けます。
プレゼンテーションの最後に、概要のスライドを示す
「親近効果」によって、受け手の理解度を向上できるからです。
「親近効果」とは、アメリカの心理学者が提唱した「最後に紹介されたものが記憶に一番残りやすく、後の判断に大きく影響する」という理論です。1
発表時間が15分よりも短い場合は、最初と最後に概要スライドを入れると、他の話ができなくなってしまいます。説明時間が少ない場合は、最後のみ概要スライドを入れ、相手の印象に残るようにしましょう。
【目的】
〇〇課題を解決するために、〇〇施策の実施を提案します。
【概要】
- 現状:△△の課題がある
- 施策:□□を活用し改善
- 期待効果:コスト▲%削減、工数▲時間短縮
2. 現状で達成したこと→未達成なことの順で説明する
提案する際に、未達成なこと(現状の問題点など)を最初に話さないようにします。
この状態を作った上司に対するダメ出しであり、上司の気分を損ねれば、提案に賛成していただける可能性が下がるためです。
たとえば、中間報告で上司の顔を立てつつ、以下のように問題提起をするとよいでしょう。

優秀な社員
前四半期は目標の80%を達成できました。
これは〇〇チームの尽力によるものです(達成したこと)。
一方で、残りの20%は△△という課題が顕在化したため、次の四半期ではこの課題解決に注力します(未達成なこと)。
マネージャー陣が達成したことを説明してから、現状の問題点を話すようにしましょう。
3. 問題点→課題→打ち手の順で説明する
ロジックツリーの構成を意識し、以下の順番で説明をします。
- 社内での問題
- その問題を解決するための課題
- 課題を達成するための具体的な打ち手
ITツールの業務活用を推進するための勉強会」を提案したい場合は以下のように伝えます。
- 問題:ITツールを”独力で”活用できる人/”十分に”活用できない人が二極化している
- 課題:スキル習得には時間がかかり、独力で業務にITツールを活かすことができない場合もある
- 打ち手:短期間で業務にすぐ使えるITツールの勉強会を開催する
上記の説明時に、数値データ(部署ごとのITツール使用者の割合など)や従業員からの意見(アンケートのフリーコメントなど)を盛り込むことで、相手を納得しやすくなります。
4. 構成・表現で減点されないようにする
提案を通すには、“反対されにくい”資料を作ることが大切です。
誤字脱字・曖昧な表現・論理の飛躍はすべて「NG理由」になります。
以下の記事でも紹介したように、完璧を目指すことは効率が悪いので、相手に指摘されて困る部分がないような資料になれば十分です。
たとえば、資料の構成は首尾一貫した内容になっているか、文章の表現は誰に対しても一義で伝わるようになっているかを確認しましょう。
NG例 問題:ITツールを使える人/使えない人が二極化している
OK例 問題:ITツールを”独力で”活用できる人/”十分に”活用できない人が二極化している
以下の投稿ではダメな文章例を紹介しているので、減点されない資料作成に役立ちます。
資料構成のチェックリスト
完成した資料が、以下の4項目を満たしていれば、上司が「通したい」と思う資料構成になっているでしょう。
- 最初に【目的・概要】を明示しているか?
- 現状→課題→施策の順になっているか?
- 上司の感情に訴えるメリットを提示しているか?
- 不備・誤解を生まない構成・表現になっているか?
まとめ|上司が思わずOKしたくなる資料の共通点
今回は提案資料を作成するためのコツをお伝えしました。
- 最初と最後に、発表内容の概要を伝える
- 現状で達成したこと→未達成なことの順で説明する
- 問題点→課題→打ち手の順で説明する
- 構成・表現で減点されないようにする
上記のコツを意識して資料を作成していただき、提案が了承されることをお祈りしています。
最後に
次に作る資料では、「目的・概要」を最初と最後に1スライドずつ入れてみてください。
たったそれだけで、提案の通りやすさが大きく変わります。
そして、上司や同僚にフィードバックを必ずもらいましょう。
改善を重ねることで、あなたのプレゼンスキルは飛躍的に向上します。
この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!
見やすいスライドやグラフ作りのコツを知りたい方は、以下の記事もお役に立てると思います。
X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
引き続きよろしくお願いいたします!