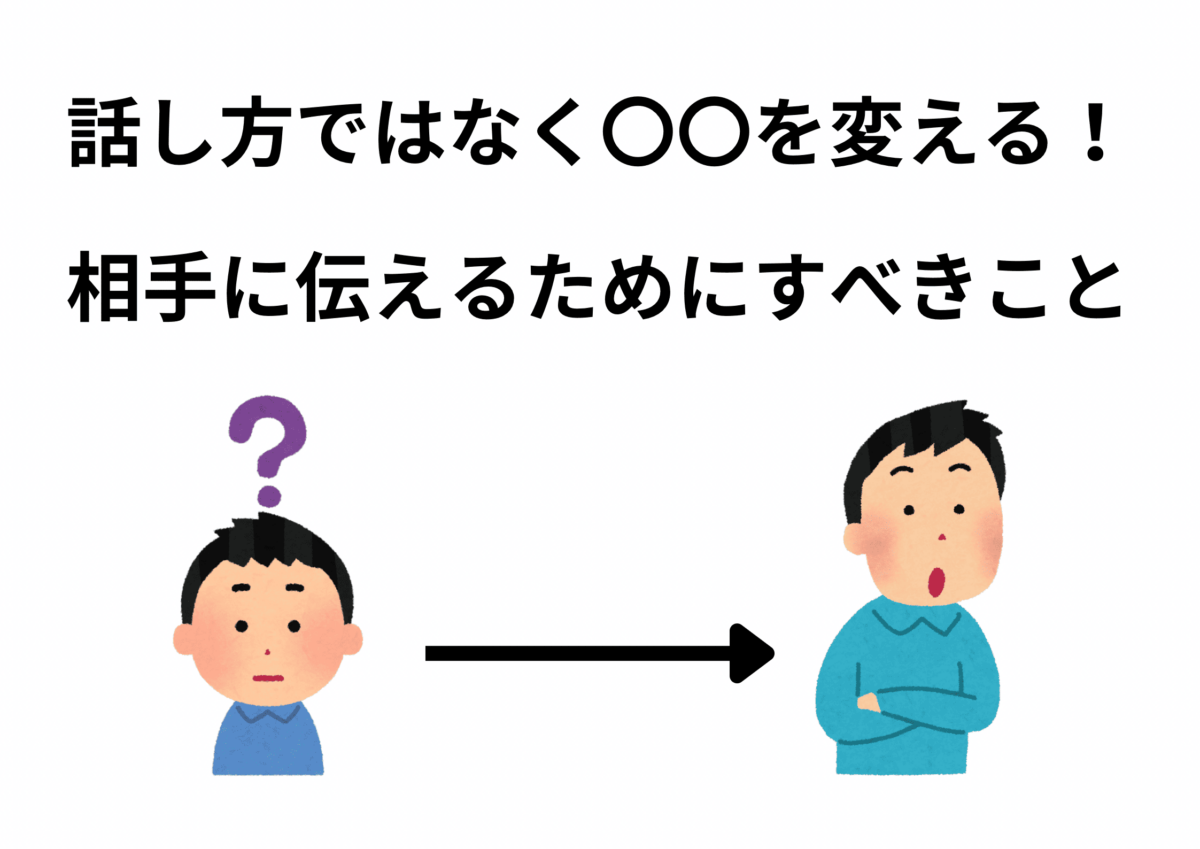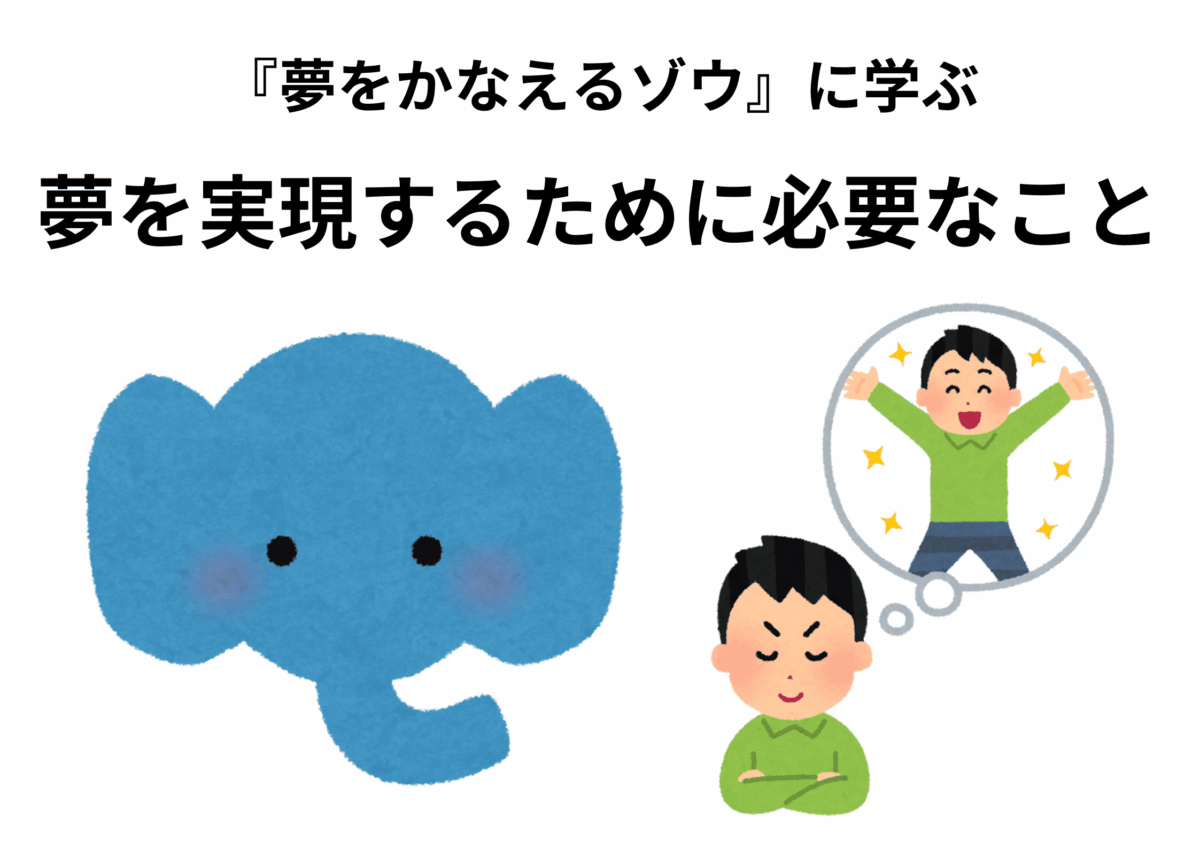- 安達裕哉著『頭のいい人が話す前に考えていること』ってどんな本?
- 話し方を変えても、自分の主張が相手に伝わらないのはなぜ?
- 自分の意見を相手に理解してもらうには?

しろろ
こんにちは、しろろです。
『言いたいことが全然伝わらない!』そう悩んだ経験はありませんか?
以前の私も同じでした。会議での提案は響かず、同僚との連携はなぜかいつもスムーズにいかない…。
特に「話が回りくどい」と指摘された時は、自分のコミュニケーション能力に心底落ち込みました。
そんな時、偶然手にしたのが安達裕哉著『頭のいい人が話す前に考えていること』1でした。
この一冊が、私のコミュニケーションに対する考え方を根本から変えるきっかけになったのです。
今回は、単なる話し方のテクニックではなく、相手に「本当に伝わる」コミュニケーションを実現するために不可欠な「考え方」の磨き方と、それを最大限に活かす伝え方の3つの実践ステップを、私の実体験を交えながらご紹介します。
『頭のいい人が話す前に考えていること』とは?
安達裕哉著『頭のいい人が話す前に考えていること』はAmazon(ビジネスライフ/労働時間・休暇)でランキング1位の本です。
3000社1万人と対峙してきた安達氏が、22年のコンサルで得た知見を1冊に凝縮しています。
本書では、「頭のいい人」が考えていることを明確にし、誰でも思考を高めて「頭のいい人」になるヒントが満載です。
例えば、「知性」と「信頼」を同時にもたらす7つの黄金法則として下記を紹介しています。
その1 頭が悪くなる瞬間、頭がよくなる時間
安達裕哉著『頭のいい人が話す前に考えていること』
その2 頭のよさを決めるのは「だれ」だ?
その3 なぜ、コンサルは入社1年目でもその道30年の社長にアドバイスできるのか?
その4 頭のいい人は、論破しない
その5 「話し方」だけうまくなるな
その6 知識が「知性」に変わるとき
その7 承認欲求をコントロールできる者がコミュニケーションの強者になれる
特に今回は、その中でも『自分の話を相手に理解してもらうための「考え方」と「伝え方」』に焦点を当て、本書のエッセンスを3つのステップとして深掘りしていきます。
ステップ1:相手が本当に求めていることを理解する
コミュニケーションにおいて、多くの人が『どう話すか』という表面的なテクニックに意識が向きがちです。
しかし、どれだけ流暢に話しても、相手が本当に求めていることを理解していなければ、あなたの言葉はただの独りよがりな情報になってしまいます。
この最初のステップは、効果的なコミュニケーションの土台を築く上で最も重要です。
まずは、相手の真のニーズを正確に把握することから始めましょう。
1-1. 相手が本当に求めているものを見過ごすと、うまくコミュニケーションできなくなる
たとえば、恋人との買い物を想像してみましょう。
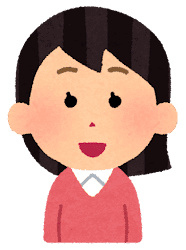
彼女
どっちの服がいいと思う?
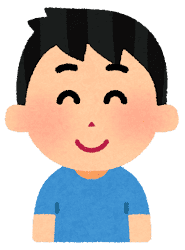
彼氏
右の服がいいと思う!
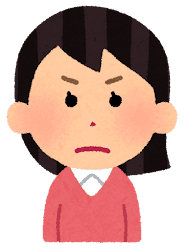
彼女
本当にそう思うの?
ちゃんと考えてくれた?
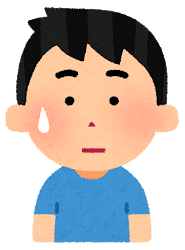
彼氏
聞かれたから正直に答えたのに…。
「どっちの服がいい?」と聞かれた場合、直感で答えるだけでは、相手は本来求めている「自分の悩みを整理するプロセス」を感じ取れません。
つまり、相手が本当に求めているのは、単なるアドバイスではなく、自分自身の考えを整理するためのサポートなのです。
自分の意見を一方的に伝えるだけでは、相手が本当に知りたいことや解決したいことを見過ごしてしまう可能性があります。
1-2. 相手が本当に求めていることを理解する方法
人に何を求められているかを明確にするために、以下のような「相手のニーズを引き出すための具体的な質問フレーズ」を活用します。
- 「この件で一番知りたいことは何ですか?」
- 「何を解決したいと考えていますか?」
- 「私がどうすればお役に立てますか?」
今回の場合だと「どうして服を悩んでいるの?」と確認した後に、相手が考えを整理するのに役立つ情報を伝えれば良かったのです。
たとえば、恋人との買い物を想像してみましょう。
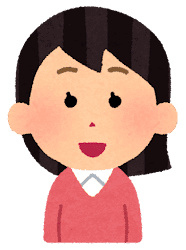
彼女
どっちの服がいいと思う?
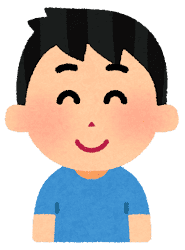
彼氏
うーん。どちらも似合ってて迷うね…。
どういうところで悩んでいるの?
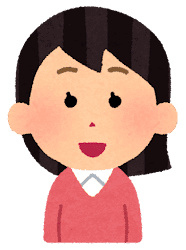
彼女
どちらがハワイ旅行に適しているか悩んでいるの…。
右の服は夏らしい色が良くて、左の服はデザインが素敵!
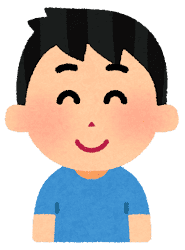
彼氏
そしたら右の服がいいんじゃない?
右の方が明るい色で気分が高まるし、デザイン的にも動きやすそう!
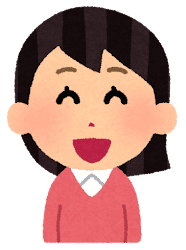
彼女
そうだね! 右の服が良さそう!
考えてくれてありがとう!
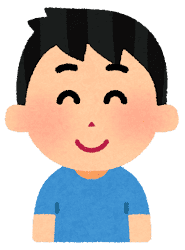
彼氏
彼女が喜んでくれてよかった!
ステップ2:信頼できる根拠を示し、偏りのない意見を構築する
信頼できる意見を構築することは、あなたの提案に重みを与え、相手からの信頼を勝ち取るために不可欠です。
2-1. 目の前の情報に飛びつく罠
テレビやSNSなどの情報を鵜呑みにして、自分の考えを示すと、相手から「この人、ちゃんと考えてないな」と思われてしまいます。
テレビなどの情報に誤りがあると言いたいのではなく、他の意見もあるかを確認してほしいです。
たとえば、2024年12月に兵庫県知事斎藤氏のパワハラ疑惑が話題になった際、SNS上には誤情報も多数存在しました。
そのため、複数の信頼できる情報源を参照し、事実に基づいた根拠を示すことが重要です。
2-2. 科学的思考力により情報の正確性を判断する
吉森氏の書籍『LIFE SCIENCE(ライフサイエンス) 長生きせざるをえない時代の生命科学講義』2で解説されている『科学的思考力』は、単なるアカデミックな知識に留まりません。
日々の情報に触れる中で、『これは本当に事実か?』『他の可能性はないか?』と多角的に検証する姿勢は、信頼できる意見を構築する上で非常に重要です。
SNSの情報だけでなく、企業レポート、業界の専門誌、信頼できる調査機関のデータなど、複数の情報源から情報を収集し、批判的に検討する習慣をつけましょう。
詳しくは、吉森氏著の第1章で解説されているので、そちらもご一読いただくと理解が深まると思います。
ステップ3:言葉の意味を正確に使い、事実と意見を明確に区別する
ステップ3では、相手に主張を理解してもらうために意識してほしい2ポイントをご紹介します。
3-1. 正確な意味で言葉を使用する
あなたの意見がどれほど優れていても、使う言葉の選び方一つで、相手への伝わり方は大きく変わってしまいます。
特に、言葉の持つ正確な意味を理解し、事実と個人の解釈(意見)を明確に区別して話すことは、誤解を防ぎ、相手に論理的で信頼性の高い情報を提供するために不可欠です。
コミュニケーションで伝える内容は、使う言葉の正確さが大きな影響を持ちます。
たとえば、Weblio辞書によれば「明瞭」3は「はっきりしていて分かりやすい」状態を指し、「明確」は「間違いのない正確さ」を意味します。
ヘッドフォンの修理依頼例で考えると、必要なのは「明瞭な音声」であって、単に「明確に聞こえる」ことではありません。
言葉の定義を明確にするには、少しでも分からないと思った文字を辞書で引くことが大切です。
普段から疑問に感じた言葉や表現は、辞書で確認し、ノートやメモに記録することで語彙力を高めましょう。
3-2. 事実と意見を分けて話す
研修でよく言われる『事実と意見を分ける』ことの重要性は、単なるルールではなく、相手との信頼関係を築き、誤解を防ぐための最も基本的なステップです。
事実は「実際に起きた事柄」であり、意見は「ある物事に対する考え」を指します。
事実と意見を分けないと、相手の求める回答とズレる場合がある
事実と意見の違いが分かっていても、事実と意見を区別して話せない人がいます。
例えば、下記のような上司と部下の会話を考えます。

上司
〇〇さんとの契約を取れましたか?

部下
契約を取れると思います。
この場合、上司は事実(契約の可否)を確認していますが、部下は意見(契約を取る見込み)を伝えています。
部下が意見を話してしまう原因は、人は難しい質問に直面すると簡単な質問に置き換えて答える癖があり、自身の都合に合わせて質問を変えてしまったからです。
事実ではなく予測(意見)のみを伝えてしまい、本来確認すべき事実が見えなくなります。
このように、事実と自分の解釈(意見)をしっかり区別して話すことで、相手に正確かつ納得のいく情報を伝えることが可能になります。
事実と意見を分けて話す方法
「伝えようとしていることが事実と意見のどちらかを考えてから話す」ようにすればよいでしょう。
会話の前に、話す内容を頭の中で一度整理し、『これは客観的な事実か、それとも私の解釈や予測か』と自問自答する習慣をつけましょう。
必要であれば、『私の意見ですが…』や『事実としては〇〇で、それに対する私の見解は…』のように前置きをすることも有効です。
まとめ
相手に自分の主張を伝えるためには、「話し方」そのものではなく、下記の3ステップの実施が鍵になるとお伝えしました。
ステップ1:相手が求めていることを理解する
ステップ2:信頼できる根拠を示して偏りのない意見を構築する
ステップ3:言葉の意味を正確に使い、事実と意見を明確に区別する
ご紹介した3ステップは、一見するとシンプルに見えるかもしれません。
しかし、これらは単なる話し方のテクニックではなく、相手に『伝わる』コミュニケーションの土台となる『思考の型』です。
この考え方を磨き、日々のコミュニケーションに意識的に取り入れることで、あなたの話は格段に伝わりやすくなり、人間関係や仕事の成果に良い影響をもたらすはずです。
最後に
『頭のいい人が話す前に考えていること』は、今回ご紹介した内容以外にも、知性を高め、信頼を築くための多くのヒントが詰まっています。
ぜひ、本書を手に取り、あなたのコミュニケーション能力をさらに飛躍させてください。
この記事で学んだことを実践した方は、ぜひコメントでその成果や気づきを教えてください!
また、『自分の話が伝わらない…』と悩んでいる同僚や友人がいたら、ぜひこの記事をシェアして、一緒にコミュニケーションの質を高めていきましょう!
X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
引き続きよろしくお願いいたします!
【記事作成に使用した書籍やウェブサイト】