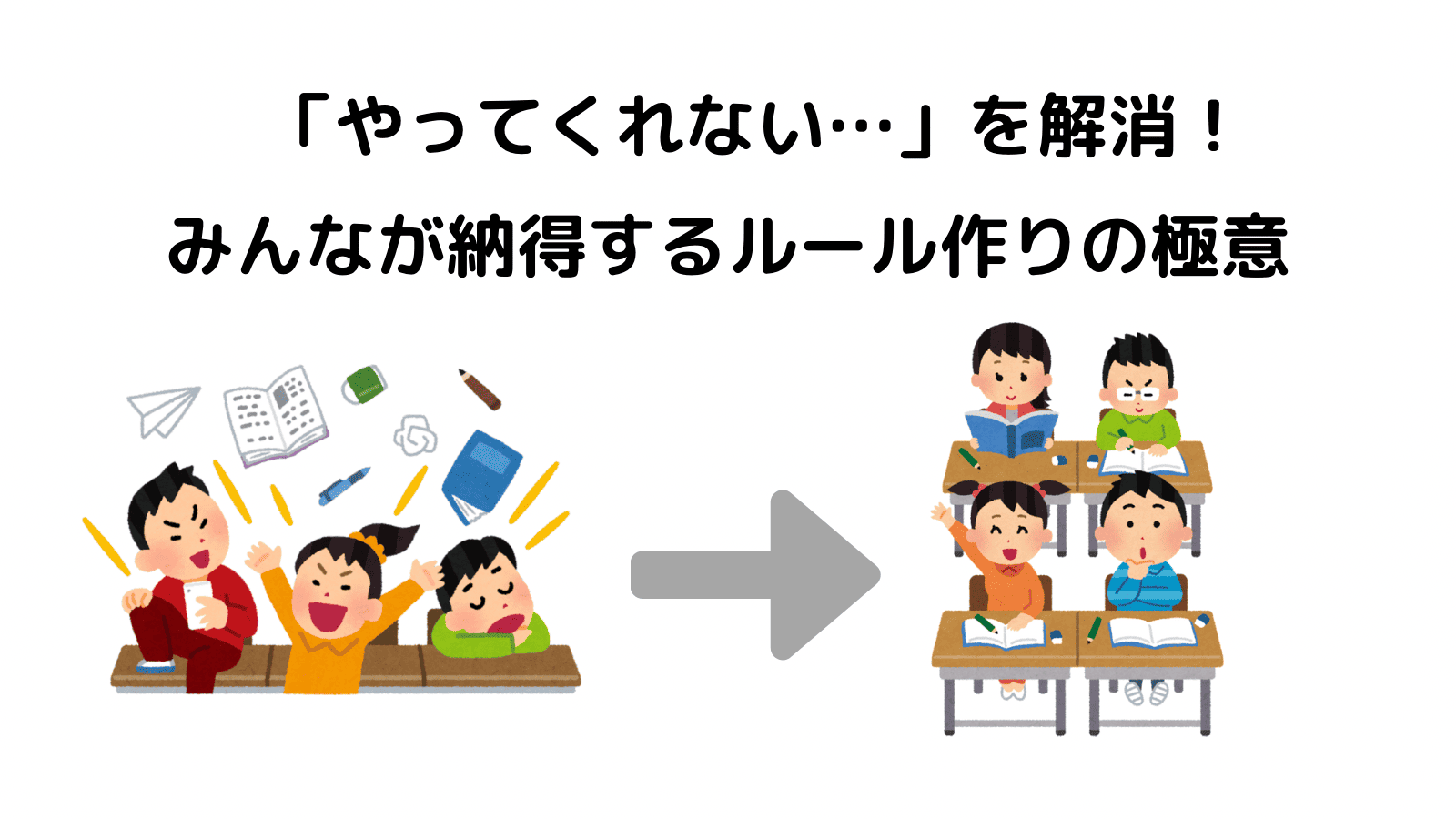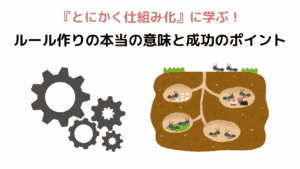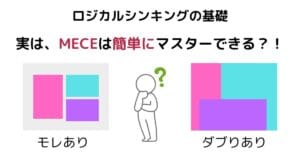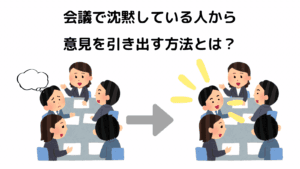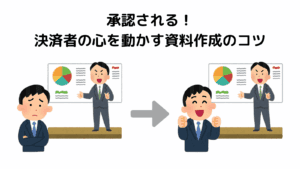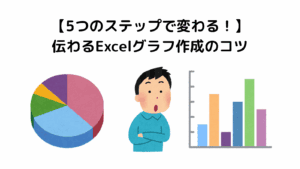- 決まりを守ってくれない理由は?
- 決まりを守ってもらうために何をしたらいい?

しろろ
こんばんは、しろろです。
決まりを守らない人に困っていませんか?
たとえば、「部屋の明かりをつけたら、退出時に消す」というルールを破る人がいますよね。
ルール違反を生む原因は、違反者が決まりを守ることにメリットを感じないからです。
今回は、ルールを守ってもらえない理由と守ってもらえるルール作りのコツについて解説します。
「決まりを作る必要性」について知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
なぜルールが守られないの?
ルール違反に関係する心理学的・行動経済学的理論
決まりを破る原因は以下の3つが関係しています。
これらをうまく活用すれば、順守してもらえるルール作りが可能です!
①現状維持バイアス1
現状維持バイアスとは、未知のものや変化を拒み、現状維持を求める心理です。
たとえば、新しいお店が気になっても、いつものお店に行ってしまうことです。
この心理により、新しいルールに切り替わろうとしても、ついいつもの行動パターンに戻りがちになります。
②内発的・外発的動機づけ2
内発的動機づけとは、自身の興味や向上心など内的な要因で動機づけられている状態です。
たとえば、自分の好きな分野のタスクに没頭することです。
外発的動機づけとは、報酬の取得やリスク回避など外的な要因で動機づけられている状態です。
たとえば、昇給のために新技術の開発に没頭することです。
内発的動機づけは長期的な成果、外発的動機づけは短期的な見返りを求める状況で効果を発揮します。
外発的動機づけの場合は報酬やペナルティに依存するため、外部要因が無ければルールを破られやすいです。
③受益者負担
受益者負担とは、利益を受ける人に負担を求めることです。
たとえば、業務担当者に作業マニュアルの作成を依頼することです。
新入りの業務担当者が配属された時に、業務マニュアルがあれば指導の負担を軽減できます。
ルールがもたらすメリットと負担が異なる場合、ルール違反が生まれます。
ルール違反が起きるメカニズム
紹介した心理学的・行動経済学的理論がどのようにルール違反に関係するかを解説します。
先ほどと同じく「部屋の明かりをつけたら、退出時に消す」というルールを元に説明します。
この決まりの場合は、特に受益者負担がルール順守・違反に関係しています。
以下の表で示すように、明かりのON/OFFで恩恵を受ける人は変わります。
| アクション | メリット | 受益者 |
|---|---|---|
| 部屋の明かりをつける | 部屋が明るくなるので作業しやすくなる | 部屋の使用者 |
| 部屋の明かりを消す | 電気使用量を抑えられので電気代が安くなる | 施設の所有者 |
部屋の使用者が電気代を支払わない場合、使い終わった部屋の明かりがついていても、消えていても関係ないです。
「明かりを消すこと」に利益を感じないので、ルール違反が起きます。
ルール作りの体験談
私の所属チームではメンバー同士は上手く連携できておらず、人によって仕事量が膨大になっていました。
そこで、連携強化と業務分散のために、チーム用カレンダーを作成して業務内容を共有しようと提案しました。
しかし、上司や一部のメンバーは賛同してくれたものの、過半数のメンバーは賛同してもらえませんでした。
「Excelに入力するのが手間」、「メンバーで話しあっておけば、何かに残さなくても平気でしょ」という意見が出たためです。
反対意見が出てしまった原因は、カレンダー導入メリットの説明が不十分だったので、メリットを感じないチームメンバーが現状維持を選択したためです。
今思えば、各メンバーの業務量と作業時間をグラフ化して示せば、チーム内で対策の必要性を周知できたと感じています。
このカレンダーの件を上司に報告すると、以下のコメントをいただきました。

上司
大半のチームメンバーに受け入れられなかったけど、ずっとこのカレンダーを使っていれば、価値に気づく仲間が増えると思うよ。
上司が言うように少しずつ理解者が増え、現在ではチームメンバーでこのカレンダーを使うようになりました。
伝え方に問題があると、本当に効果があるものでも利用できなかったり、使用までに時間がかかってしまうのだと勉強になりました。
ルール作りの手順
前章で説明した失敗を乗り越え、その気づきを活かしたルール作りの手順をご紹介します。
ここでは、連携強化と業務分散ための仕組み作りを例にして説明します。
Step1:ルールの目的を明確にする
まずは何のためにルールを作りたいのかを明確にします。
先に手段を選択してしまうと、手段が目的となり、本来のゴールを見失う可能性があるからです。
今回の場合は、連携強化と業務分散による働きやすさの改善を目指します。
みんなが改善したいと思う目標を掲げることで、現状維持バイアスを抑えることができます。
Step2:複数の選択肢とそのメリット・デメリットを洗い出す
最初から1つの案に絞らず、様々なアプローチを検討します。
メリットとデメリットを考慮することで、内発的・外発的動機づけと受益者負担を活用できる選択肢を選べます。
| アクション | 対象者 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| チームカレンダーの作成(Excelなど) | 全員 ※保守は1人 | ・決まった形式がないので、好みのレイアウトを作成できる | ・カレンダーの作成・更新に手間がかかる |
| タスク管理ツールの使用(Plannerなど) | 全員 ※保守は1人 | ・土台がすでにあるので、タスクを入力するだけでよい | ・タスクの入力が手間である ・形式に決まりがあるので、自由度は下がる |
| リーダーに業務アサインを考えてもらう | リーダー | ・チームメンバーは何もしなくてよい | ・管理職の仕事が増える ・メンバーの主体性を損なう可能性がある |
| 定例会議で業務調整の時間を作る | 全員 | ・みんなで話し合い、その場で仕事の振り分けを決定できる | ・他の議題で使える時間が短くなる |
アクションの候補が1つしか思いつかない場合は、下記の記事で解説しているように、その行動の逆を考えてみるとアイデアが浮かぶかもしれません。
Step3:対象者に意見を聞く
ルールの対象となる全員から意見を集め、実際にどのような懸念点や改善点があるかを把握しましょう。
これにより、一方的なルールの押し付けではなく、納得感のある決定が可能になります。
特に、個別に話を聞くことをオススメします。
周囲の人に気遣い、自分の意見を言えない人からも意見を聞けるからです。
会議中に意見を集めたい場合、以下の記事を参考に発言しない人の主張も集められるとよいでしょう。
チームメンバーから「対面で仕事の割り振りを決めた方が早い」、「誰が何を担当するか記録を残した方がよい」といった意見が出ました。
Step4:ルールを決める
得られた意見をもとに、誰がメリットを享受し誰が負担を担うかを加味して、最適な仕組みを選びます。
今回のケースでは、「定例会議で業務調整を行い、チームカレンダーで業務割り振りを記録する」ことに決まりました。
ただ、受益者の負担が大きくなる選択をする場合は、別の手段にするなどチーム全体のバランスを重視しましょう。
このルール設定では「連携強化と業務分散による働きやすさの改善」を目的としており、受益者に負担がかかってしまうと本末転倒なので。

Step5:ルールの周知と導入メリットの説明
ただ「決まりを作ったので守ってください」と伝えるのではなく、なぜこのルールが必要なのか、その背景と導入によるメリットを丁寧に説明しましょう。
自分に利益のない規定により行動を制限されたくないので、ルール作成の経緯がないと反発される可能性が高くなります。
資料や具体的なデータを用いて伝えると、理解を得やすくなり反発も和らぎます。
以下の記事は、ルールを周知するための資料作成に役立てるため要チェックです。
まとめ
決まりを守ってもらうには、ルール違反が発生する原因を理解することが重要です。
現状維持バイアス:未知のものや変化を拒み、現状維持を求める心理
内発的動機づけ:自身の興味や向上心など内的な要因で動機づけられている状態
外発的動機づけ:報酬の取得やリスク回避など外的な要因で動機づけられている状態
受益者負担:利益を受ける人に負担を求めること
そこから、以下のステップで目的・課題に基づいた具体的な施策を段階的に実践することで、全員がその価値を実感できる仕組み構築に繋がります。
Step1:ルールの目的を明確にする
Step2:複数の選択肢とそのメリット・デメリットを洗い出す
Step3:対象者に意見を聞く
Step4:ルールを決める
Step5:ルールの周知と導入メリットの説明
これらのポイントを押さえれば、「やってくれない…」という悩みは着実に解消されるはずです。
最後に
この記事では、「やってくれない」理由と、それを解消するための実践的なルール作りのプロセスを整理しました。
この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!
X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
引き続きよろしくお願いいたします!
【記事作成に使用したウェブサイト】