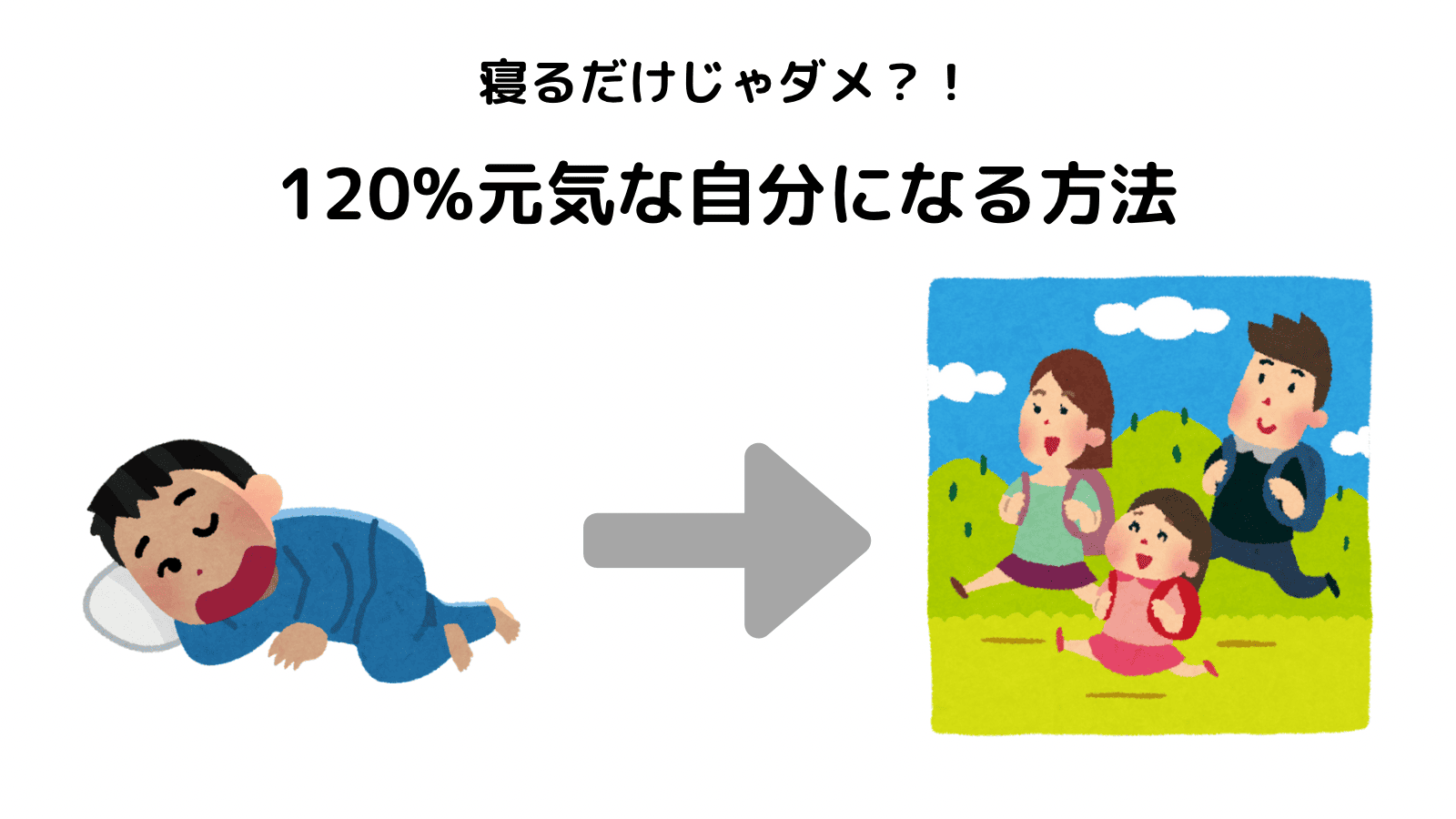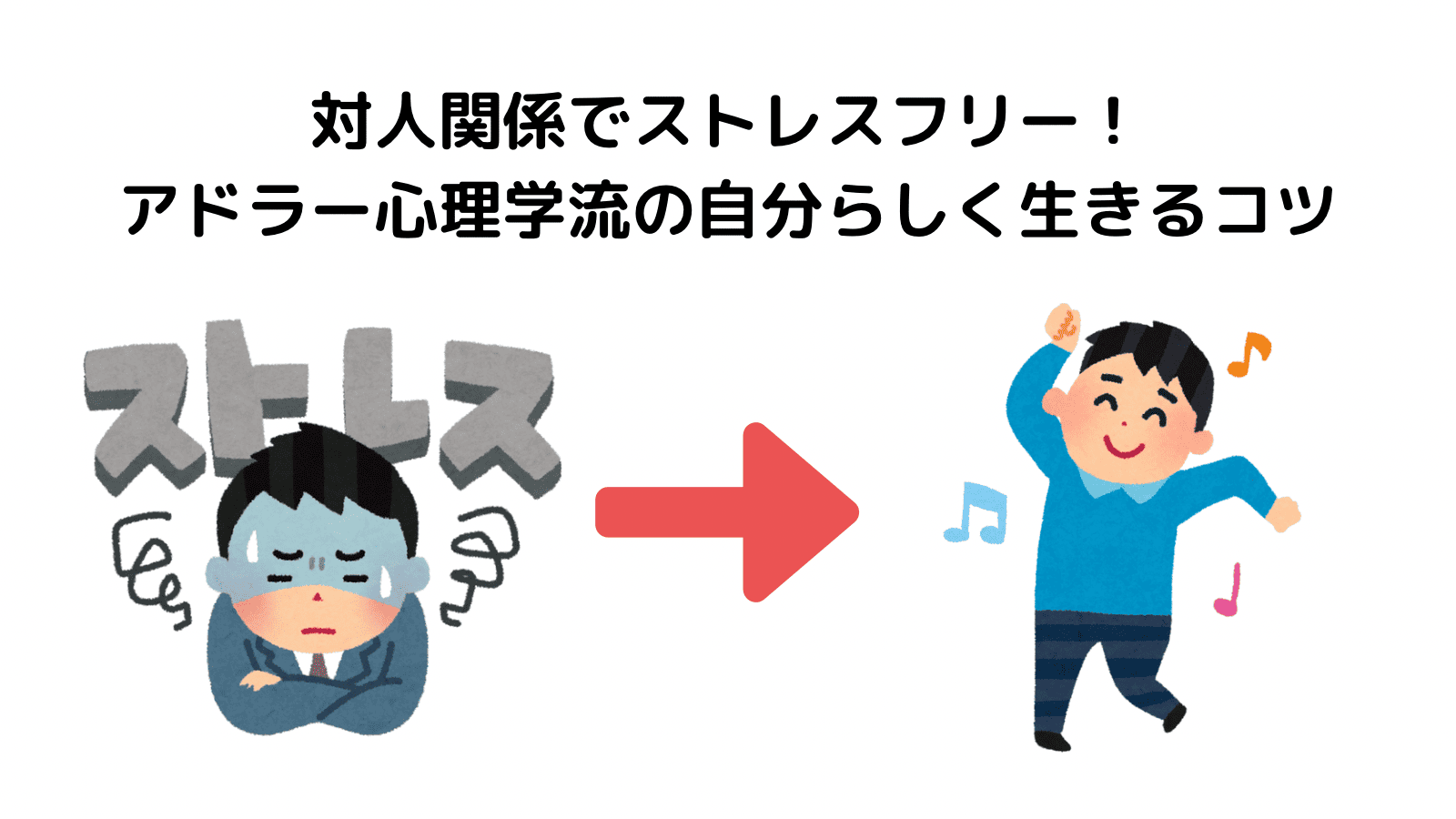- なぜ人は疲れるのか?
- 疲労回復の効果的な方法は?
- どうすれば120%元気になれるのか?

しろろ
こんにちは、しろろです。
朝起きても疲れが取れていない…
休日にゴロゴロしても、逆にだるくなる…
そんな経験、ありませんか?
現代人の約8割が仕事や育児で慢性的な疲労に悩まされています(日本リカバリー協会の調査1)。
ただ寝るだけでは、実は逆に自律神経が乱れ、体の回復が不十分になってしまう可能性があるのです。
今回は片野秀樹著『休養学: あなたを疲れから救う』2をもとに、超回復理論による疲労解消と元気アップに必要な正しい休養法を詳しくご紹介します。
なぜ人は疲れるのか?
疲労の定義と原因
疲労とは、身体的および精神的な活動により、本来発揮できる能力が低下した状態です。
活動に伴うエネルギー消費の結果、呼吸により取り込まれた酸素から活性酸素が発生します。
激しい運動や精神的ストレスの多い状況では、必要以上に活性酸素が生み出され、細胞を傷つけます。
結果として細胞の機能が一時的に下がり、活動能力の低下と疲労感を引き起こします。
疲労は身体からのサイン
発熱や痛みと同じく、疲労は身体からの危険信号です。
やりがいや責任感により、一時的に眠気や疲労を感じなくても、放置すれば内分泌系・神経系・免疫系に不調が現れてしまいます。
活動・疲労・休養・活力の4ステップで充電!
従来の疲労解消サイクルでの限界
私たちは活動→疲労→休養のサイクル(仕事や勉強し→疲れて→休む)で生活をしています。
しかし、このサイクルだけでは、元の体力の約50%までしか回復できないという現実があります。
「活力」をプラスする新しいサイクル
効果的な休養方法は、活動→疲労→休養→「活力」の4ステップです。
ここでいう「活力」とは、軽い負荷をかけることで体にポジティブな刺激(=超回復)を与えることです。
疲れているけど多少は余裕がある時に軽い負荷をかけ、その後にしっかり休養します。
その結果、活動する時よりも体力がつき100%以上の自分になれます。
“活力”におすすめな負荷は下記のものです。
- 自分で決めたもの(例:英会話)
- 仕事に関係ないもの(例:DIY)
- 自分が成長できるもの(例:資格の勉強)
- 楽しむ余裕があるもの(例:ウォーキング)
- 肉体的・精神的の両方に関わるもの(例:百名山を制覇する)
どうして「活力」をプラスすると体力がアップするの?
スポーツでおなじみの「超回復理論」に基づいて、次のような流れで体力が向上するためです。3
負荷 → 疲労 → 回復 → 元より高い状態で戻る
アスリートはこの原則を活かして、激しいトレーニングの後には必ず適切な休養をとることで、より高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
この「超回復」の概念は、1950年代に旧ソ連の生理学者ヤコブレフ(Yakovlev)によって提唱され、後にViru(2002)らによって国際的に広まりました。
この考え方は、アスリートだけでなく、ビジネスパーソンにも応用できる重要な戦略です。
仕事や日常の中で意図的に「回復の時間(=活力をプラスする時間)」を取ることで、心身のパフォーマンスを持続的に高めることができます。

元気になるための注意点
疲れ切っている時に負荷をかけないようにしましょう。
回復できていない状態で刺激を与えると、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。
Banisterら(1985年)のフィットネス–ファティーグ理論4によると、パフォーマンスは「成長(フィットネス)」と「疲労(ファティーグ)」のバランスで決まります。
短期的には疲れが残りますが、長期的には回復を経てパフォーマンスが向上するという“二面性”があるのです。
疲労が強い時は、まず“疲労をゼロに近づけること”が最優先です。
「まだちょっと疲れてるけど、動けるかも」と感じられるタイミングで、軽い負荷をかけると良いでしょう。
たとえば、体力を10としたとき、軽い刺激で7~8まで落ちても、適切に休むことで11まで超回復できます。
このサイクルを繰り返すことで、11→12→13…と体力が段階的に向上していきます。
疲労回復効果を最大化するためには?
休養タイプを組み合わせる
効果的な休養を実現するためには、以下の7タイプの休養を組み合わせると効果が倍増します。
- 生理的休養
- 休息タイプ(例:コタツでゴロゴロする)
- 運動タイプ(例:ランニング)
- 栄養タイプ(例:健康的な食事を食べる)
- 心理的休養
- 親交タイプ(例:友達や家族と話す)
- 娯楽タイプ(例:クラシック音楽を聴く)
- 造形・創造タイプ(例:マインドフルネス)
- 社会的休養
- 転換タイプ(例:旅行)
たとえば、家族でハイキングに行く場合、下記のように複数タイプの休養が取れます。
- たくさん歩く→運動タイプ
- 栄養バランスのいいお弁当を食べる→栄養タイプ
- 家族とお話しする→親交タイプ
- 歌う→娯楽タイプ

最初から休養を組み合わせなくていいので、まずは一つずつやってみて、その後に組み合わせてみましょう。
自分のやりたいことをする
休養は、ストレスを感じない自分が本当に楽しめる活動を選ぶことが大切です。
相手に合わせる必要はありません。
自分がワクワクする趣味や習い事が、結果として疲労回復とパフォーマンス向上に直結します。
ストレスを解消して、元気になった体験談
仕事が忙しくてボロボロに
毎日残業が続き、月に1回は38度以上の高熱が出る時期がありました。
休日は外に出る気力がなく、予定がない日は家でダラダラしていることが多かったです。
実家で過ごしてストレスを解消
ある週末に家族との予定のために実家へ帰り、その日にコロナを発症しました。
実家には一泊二日で滞在予定でしたが、七泊八日も泊まることになりました。
久しぶりに家族と長い時間を過ごしたことで、大切な人と話したり、テレビを見たりすることで疲労が回復することがよく分かりました。
今までは年1-2回しか実家に帰っていなかったのですが、頻度を増やすことにしました。
まとめ
疲労とは、心と体が発する「そろそろ休んで」のサインです。その原因には、活性酸素などによる目に見えないダメージも関わっています。
だからこそ、ただ寝るだけの休息では不十分です。
本当に元気を取り戻すには、活動→疲労→休養→活力の4ステップが必要です。
「軽い負荷」×「しっかり休養」による超回復のサイクルを取り入れることで、私たちは“元の自分”ではなく、“120%元気な自分”に戻ることができます。
また、7つの休養タイプを上手に組み合わせて、自分が心から楽しめることを選ぶことで、疲労は「回復」にとどまらず、「エネルギーの再充電」に変わります。
多くのことをこなすためには、まず“ちゃんと休む”ことから始めましょう。休むことは、サボりではなく、次の一歩を強くするための準備です。
最後に
今回の記事では、『休養学: あなたを疲れから救う』を参考にまとめました。
休養学に関心がある方はぜひご一読ください。
もしも仕事で悩みがあり、誰かに相談したいと思われている方はこちらの記事が参考になると思います。
120%元気になれた方は、以下の記事をご確認いただき、夢の実現に一歩近づいていただければと思います。
この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!
X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
引き続きよろしくお願いいたします!
【記事作成に使用した書籍やウェブサイト】
- 日本社団法人リカバリー協会. “日本の疲労状況2024”. (参照 2025-06-04). ↩︎
- 片野秀樹. 休養学: あなたを疲れから救う. 東洋経済新報社, 2024, 216p. ↩︎
- Viru, Atko (April 17, 2002). “Early contributions of Russian stress and exercise physiologists”. Journal of Applied Physiology. 92 (4): 1378–1382. ↩︎
- Banister E, Calvert T, Savage M, Bach T. A systems model of training for athletic performance. Aust J Sports Med. 1985;7(3):57–61 ↩︎